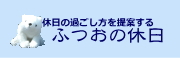- �͔|�i��
- �x�j�A�Y�}�i�c���w���j
- ��܂�
- �Y������
- �A�t��
- �s�ɂ���߂�y�̒��ɖ��ߍ��ށB
- ����
- ���n�͔�4kg�A�����엿40g
- �Ǘ�
- ��{�I�ɒǔ�͕K�v�Ȃ����A2~3�T�Ԍ�̐������x����J�������̑����엿���{���B�Ă͖��Ԃ�����B
- ���n
- 10~11��
�s���N�x�͔̍|�ɂ��āt
- ���ԁE����
- 30cm�i�����̊��ԁF30cm�j
- �ڕW���n��
- 50��
2012�N5��7���@�A����


�T�c�}�C����A�����܂����B�c�͑O��(5/6)�ɃW���C�t���{�c�ōw�����܂������A���X�ō�N�w�������c�Ƃ���ׂČ��C����܂���ł����B������1�����ɂ����܂������A����ł��t�������ꂽ�����ɂȂ��Ă��܂��B���T���ɉJ�����҂ł��邱�Ƃ���A���̓��ɐA�������邱�Ƃɂ��܂����B�c��20�{�i400�~�j�ł�����2�̐��ɊԊu���l�ߋC���ɂ��ĐA�������̂�1.5���ōς݂܂����B
2012�N5��13���@�͂ꂽ?!

�����͉Ƒ��ɐ��������肢���Ă���Ă�����Ă��܂������A�c�O�Ȃ��ƂɌ͂�Ă��܂����悤�ł��B���R�͈ȉ��̂����ꂩ�A�܂��͕������Ƒz�����Ă��܂��B�@�c�̑I�ѕ��̌��A�A�����̋C���͍��������[�͗������y�����Ⴂ�A�B蹂��~��A�����������r���Ȃǂُ̈�C�ۂ̂��߁A�c�����������ŗh���ė��������Ȃ������B
���N�T�c�}�C����A���Ă���n���̔_�Ƃ̐A�����͖����̂悤�ł��B���̂��߁A��L�̇A��������������Ȃ��ł��B
�NjL�F��؍͔|�̋��ȏ��ɂ́A�u�����������╗�ɓ�����ƍ��t�����Ɍ͂�Ă��܂����Ƃ�����v�Ə�����Ă��܂����B���Ύs�Ȃǂŗ�������������悤�ȃw���ȋC�ۏ����i�����j���������Ƃ������̈�Ƃ��ċ��������܂��B
2012�N5��26���@�����c��


���������ƂɂقڑS�ẴT�c�}�C���������ł��B�s���N���オ���Ă��܂��B�m���Ɍ͂ꂽ�̂�1���A������Ȃ̂�1~2������܂����A����ȊO�͖��Ȃ������ł��B�T�c�}�C���̐����͂̋����������܂����B�͂ꂽ���͋Ă����A�����L�тĂ�����ꕔ������đ}���Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��i���������A���n�Ɏ��邩�ǂ����m��܂���B�P�Ȃ�v���t���ł��j�B
2012�N6��10���@�t������������



�t�������炩�ɑ����Ă��܂����B�ꎞ�͕c�̒lj��w�����l���܂������A�悩�����悩�����B�����L�тĂ�����A���N�͖����H���Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��B���₫�ɁA���̑���ɃT�c�}�C���̖�������œ���Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��B
2012�N6��24���@�r���o�߁F����



����2�T�Ԃɂ����ԗt���������܂����B
2012�N7��5���@����


���̂Ƃ���ׂ̃J�{�`���̐����Ɉ��������܂����A�T�c�}�C�����傫���Ȃ��Ă����̂œ����̒D���������n�܂肻���ł��B
2012�N7��21���@��


���܂����̖����L�тĂ��܂������A�ׂ̃J�{�`���̐��������������邽�߁A����ł��u�����������L�т��v�Ɗ����Ȃ��ł��B
2012�N8��4���@����


�J�{�`���Ɠ����̒D�������̌��܂����Ă��܂��B���̂Ƃ���J�{�`�����D���̂悤�ł��B�T�c�}�C���̓J�{�`������������Ԃ������̂ŁA�J�{�`���̌�Ɋ撣���Ă��炢�܂��傤�B
2012�N9��1���@���Ԃ�


�T���_����苎��A�N�H���Ă����J�{�`�����̂����܂����B�T�c�}�C�������ɂȂ����̂ŁA���߂Ă̖��Ԃ������܂����B���ɍ����o�Ă�����������A���X�x�����܂������B
2012�N9��15���@�o��

�J�{�`���Ɏז�����Ȃ��Ȃ����������A�T�c�}�C�����炵���Ȃ�܂����B�ŋ߂ł͔��ɍs���x�ɖ��Ԃ����Ă��܂��B
2012�N9��23���@�o��


�J�̒��ł��������Ԃ����܂����B���ɍ��������Ă����������A���������Ă�����������������Ȃ��ł��B
2012�N10��6���@���n

�q�ǂ��ƃT�c�}�C�����n���悤�Ƃ����b�ɂȂ�A������2�ӏ��@��グ�Ă݂܂����B�T�c�}�C���͏����������C�����܂����A�傫���̂��������Ă���ǂ��Ƃ��܂��B
2012�N10��20���@���@��


���ߏ������U���ăT�c�}�C���@�肵�܂����B�܂��ŏ��ɁA�Е��̐��̖�������ď������܂����B



�ό��_���ɂ���Ắu�ҏ��̉e���ň炿���������N�̃T�c�}�C���@��𒆎~�v�ƕ����Ă��܂��B������l����Ə\���ȑ傫���Ǝ��n�ʂ������悤�Ɏv���܂��B
2012�N11��4���@���n


�q�ǂ������n�������Ƃ����̂ŏ����@��N�����Ď��n���܂����B���̏T���Ɏc�肷�ׂĂ����n���悤�ƍl���Ă��܂��B
2012�N11��11���@���N�Ō�̎��n

���̔����ȏォ��̎��n�ł������A���܂ł̎��n1����̊����������ɂ��ւ�炸�A���n�ʂ͏��Ȃ��A�T�c�}�C�������Ԃ�ł����B����܂łƂ̈Ⴂ�́A����@�����ꏊ�͖��Ƃ̉e�ɂȂ鎞�Ԃ������A���Ǝ��Ԃ����Z�����Ƃł��B����̎��̌o������́A�T�c�}�C���͓��Ǝ��Ԃ̉e��������̂��v���܂��B
�ƒ�؉�������Ă�����́A��؍͔|�Ɋւ���{�����������낤�Ǝv���܂��B����������ɋ������������Ȃ̂ł�����A���L�̖{���Ŗ�̌��������A�h�{����������H�ו��ɂ��Ēm�����L���Ă͂ǂ��ł��傤���Ƃ�����Ăł��B
�ʓX�u�z�n��~�v���` ��̑I�ѕ��A�������B�\�������̊�b�m��